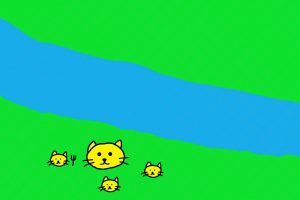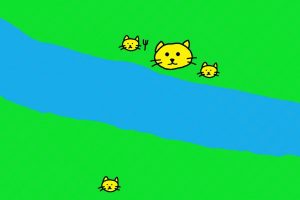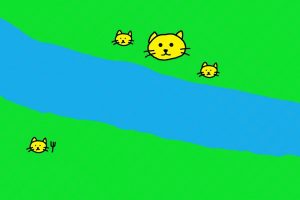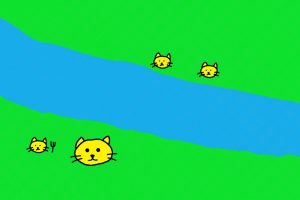この記事の構成
- 1ページ目 龍安寺石庭の意味、枯山水の意義、「虎の子渡し」説、「15(不完全)」説、15個すべての石は見えないのか?、「心」説
- 2ページ目 石「五智如来」説、「十六羅漢遊行」説、「七五三」説、「カシオペア(星座)」説、「清少納言知恵の板」説、
- 3ページ目 龍安寺石庭の歴史と作られた時期の謎、築地塀の謎
- 4ページ目 誰が石庭を作ったのか?
- 5ページ目 石庭以外の龍安寺のみどころ
- 6ページ目 石庭の四季、アクセス、参考文献
このページのもくじはこの下にあります。
15個の石の意味、みどろこと謎
- 通説的見解では、龍安寺石庭は”虎の子渡し”という故事を具現化する庭であるとされ、龍安寺もこの見解をとる。
- 虎の子渡しとはものごとをうまくやりくりするといった意味がある。
- 但し、龍安寺石庭は伝統的な日本庭園であり、一義的には山と海を意味している。また、後期枯山水庭園に属する。後期枯山水庭園は経典、水墨画などを具体化することに特徴があり、故に庭園の意味が問題になる。
龍安寺石庭概観
まずは龍安寺石庭を概観してみましょう。龍安寺石庭の大きさは、約25×10メートルです。この中に、白い砂が敷き詰められ、15個の石が5のグループに分けられて配置され、それぞれ苔の島に乗っています。

石庭の反対側にあるつくばいについては以下のリンクを参照してくれ。


雪が降ったから撮ってきたよ
虎の子渡しの庭
概説
石庭はこのようになっています。石が15個あり、5つのグループに分かれます。長方形に見えますが、実際には六角形です。
根拠
本件庭園の意味としては、宗の時代の故事に基づく虎の子渡しが一番有名かつ通説的見解です。龍安寺は度々火災に見舞われ、多くの文書を逸失していることから、根拠は不明で、現在まで慣習として「虎の子渡しの庭」として理解されています。
この説、並びに石庭が最初に文献に出てくるのは、儒医の黒川道祐が1681年に著した『東西歴覧記』です。

『東西歴覧記』っつーのは、後述する『雍州府志』を編集するための調査の記録みてーなもんなのよ。
ここで、”方丈ノ庭二石九ツアリ、是ヲ虎ノ子渡シト云へル”とあり、根拠は示されておらず、慣習としてそのように解されていたことが看取できます。原文は国立国会図書館のデジタルコレクションでみることができます。109ページの左上の方にあります。
また、黒川道祐が記した『雍州府志』では、石は大きいものが9個あり、”其布置非凡巧之所及也”(一般には解しがたいといったような意味)と記載されています。
続いて、近衛家熙の侍医たる山科道安がその言動を記した『槐記』によると、当時第一級の知識人であり、大乗大臣たる家熙も龍安寺庭園の意味につき合点がいかない旨述べています。
このように虎の子渡しの意義、根拠については確固たる証拠はありません。
虎の子渡しの意義
この説は13世紀の『癸辛雑譏』という書物の「虎引彪渡水」を端とするものです。虎が子を産むと、3頭のうち1頭は彪(ひょう)で、母親がいないと他の子をたべてしまいます。この状況のなか、母虎が子を川の対岸に連れて行くという故事です。言葉で説明すると分かりにくいので、絵を用いて説明します。
大きい虎が母虎、フォークを持っているのが彪、のこりの頭が子虎です。これかた対岸に向かいます。母虎は一度に1頭の子しか対岸に運べません。
母虎は彪を連れて対岸に行きます。
その後、元の岸に戻ります。
その後、1頭の虎を連れてきます。このまま元の岸に戻ると、子虎は食べられてしまいます。
そこで、母虎は彪を連れて帰ります。
今度は、彪を残し、もう一頭の子虎を対岸に連れて行きます。
子虎を残し、母虎は彪を迎えに元の岸にもどります。
最後に彪を連れて、対岸に行きます。これで全員が対岸に渡ることができました。
以上のような動作から、「虎の子渡し」とは生計をやりくりする、とか、ものごとを順次手渡すこと、といった意味が生まれます。これが通説的見解で、龍安寺でもこの説が説明されています。
ただし、出てくるトラさんは4人なのに、石の数は15個、また、石のグループは五個しかないためこれらにどのような紐帯があるのかは不明です。
尚、重森美玲著『枯山水』の中で、龍安寺の石が平行に配されているが、これは、西芳寺の夜泊石に範をとったものであるところ、夜泊石は虎の子渡しと解されたことがある旨適示されていますが、刮目すべきと解されます。

枯山水庭園の多くは、仏教に関するものが表現されています。例えば、蓬莱山などはよく石で表現されます。これに対し、虎の子渡しは直接仏教には関係がありませんが、南禅寺の方丈南側の庭園などで取り入れられています。
龍安寺石庭の意味と枯山水の意義, IDEST, 山と海か川
龍安寺の石庭は伝統的な日本庭園ですので、まずは日本庭園が意味するものを詳らかにします。

龍安寺の石庭は「山水」を表しています。固有の日本の庭園は「山水」、すなわち自然の風景を表します。『作庭記』によれば、石と水を用いて海と島や山の風景を表すのが原則ですが、水を使わず「山水」を表現する場合を”枯山水”といいます。龍安寺の石庭はこの枯山水を発展させたものなので、海、湖、若しくは川と山、若しくは島のいずれかを表現しています。

確実なのは、海/湖/川と山/島を表してるってことだけだ。
他の見解は論拠が脆弱だったり、撞着してたりするから参考に止めておいてくれ。つーか根拠がないものが多い。

山と海、i.e., 自然は信仰の対象にもなるよ。以下のリンクを参照してみてね。龍安寺の石庭が作られた時は、あそこは本来は何もおいちゃいけないとこなんだったんだけど、石が置いてあるのは信仰の対象たる自然に擬制されてるからだよ。


まとめ
- 事実として、虎の子渡しの庭と解されているが論拠は不明である。
- 日本の伝統的な庭園であり、海/湖/川と山/島を表現している蓋然性がオニのように高い。
- 他、数多の解釈があるが、論拠は脆弱である。
以下、著名なものを列挙します。前述の通り、龍安寺石庭は難解を極めますところ、様々な憶測があり、これ自体は首肯されます。
15
石庭には全部で15個の石が配置されています。15という数字は、月が15日で満ちることから、東洋では完全を意味します。龍安寺石庭ではこのうち14個しか見えないので、完全の中の不完全を意味してるというものです。

太陰暦は明治時代までは我が国の生活と密接不可分だったからな。祇園祭も太陰暦が基準になって日程が組まれてんのよ。
「心」
漢字の「心」という字を表しているという説です。禅では言葉を介さずに経験を通じ理解/体感するということを表しているとする説です。